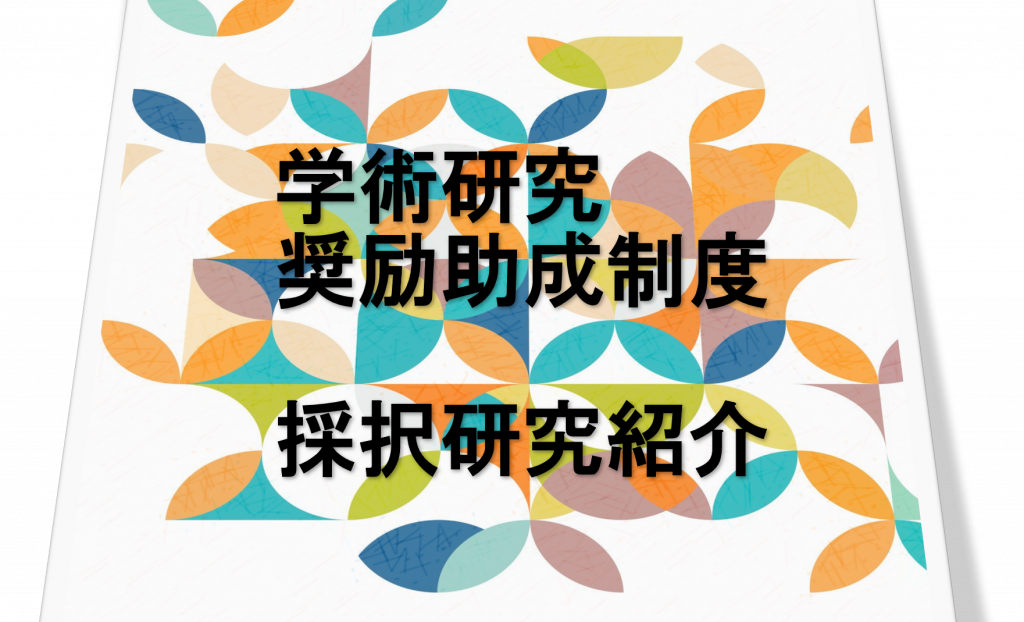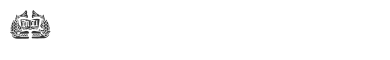ピックアップコンテンツ
- ホーム
- ピックアップコンテンツ
- 【採択研究紹介】カーボンニュートラル物質改質技術研究センター
研究センター部門 令和5年度 研究センター推進事業費 研究代表者:竹田圭吾(理工学部・教授)
研究内容・今後の展望
「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える」ことを世界共通の長期目標とした「パリ協定」が2015年12月に採択された。我が国においても「脱炭素社会」を今世紀後半に実現することを目指すとともに、2020年10月の臨時国会にて「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2050年までに二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの排出を「実質ゼロ」にすることを目標とした様々な活動が行われている。このCO₂の実質排出量「ゼロ」を目指すカーボンニュートラルのシステムを実現するには、主に化石資源に依存してきたエネルギーシステムに対し、省エネルギー化の促進とともにCO₂排出量の少ないエネルギー資源への転換、再生可能エネルギーなどCO₂フリーなエネルギーを利用するシステムが必須である。また、液体系炭化水素燃料の利用や炭素源を必要とする化学品製造などの分野では、CO₂の循環的利用により、実質的に大気中CO₂を増加させないことも重要である。そこで、世界各国でCO₂を分離・回収して、燃料・化学品へ物質変換し利用する技術(CCU:Carbon dioxide Capture and Utilization)が注目を集め、とくに大気中のCO₂削減に寄与する重要な技術として光触媒的CO₂還元や、CO₂を原料とした触媒的物質変換(ドライリフォーミング)技術が広く研究されている。しかし、CCU技術におけるCO₂変換(還元)には、熱力学的に大きな吸熱反応過程が必要となり、現在主流の熱化学的プロセスのみでは対応しきれず、反応プロセスを促進させる触媒技術の発展に大きな期待が寄せられている。
各プロセスに使用される触媒に関する研究においては、例えば人工光合成用に研究開発されている光触媒の光変換効率は現状~10%程度と、植物の光合成(0.2~0.3%)を大きく超える効率を実現することに成功しているものの、更な効率化、高耐久化が求められるとともに、太陽光変換効率を低下させずに更に大面積化を実現することが、社会実装するために必要とされている。また、CO₂のドライリフォーミングに使用される触媒についても、ニッケルや金属酸化物などをベースとした触媒が実用化されているものの、CO₂の分解に伴い発生する炭素の析出(コーキング)による変換効率の低下が問題となっているように、効率と耐久性を高次元で維持する新たな触媒または変換システムが求められており、これらの課題の達成には更なる基礎研究による学術基盤の構築が強く求められている。
そこで本センターでは、特にそれらCO₂変換反応プロセスにおいて極めて重要な触媒技術に着目し、1)触媒材料の最適化による更なる反応の高効率化と高耐久性の実現、2)新規触媒(複合)材料の探索と新たな合成技術の検討、そして、3)プラズマ反応場を利用した新しい触媒反応系の構築、に関する研究を遂行している。これらの研究遂行のため、本研究センターでは以下の4つの研究班を構成し、プラズマ(触媒)反応系、無機系、有機系、そしてカーボン系と広く様々な触媒材料を候補として検討するとともに、それらの複合材の可能性についても探求している。以上の研究を1)プラズマ(触媒)反応班:プラズマの生成・制御技術の専門家である電気電子工学科の竹田、プラズマ生成に重要な高電圧・パルスパワー研究に従事する電気電子工学科の村上准教授、2)無機系触媒班:スパッタ成膜や化学合成に詳しく機能性酸化物の合成と応用に従事する電気電子工学科の太田教授および応用化学科の才田准教授、3)有機系触媒班:キノン系や錯体分子など有機分子を用いた人工光合成を長年研究している応用化学科の永田教授、そして、4)カーボン系触媒班:カーボン系材料およびその合成の専門家である電気電子工学科の平松教授(および竹田)、の計6名の4班で従事している。
以上のように、本研究センターでは、本学における触媒およびその応用技術を熟知する研究者らを集め、CO₂を原料とした人工光合成やドライリフォーミングなどに使用される触媒反応の更なる高効率化および高耐久化を目指した研究活動を実施し、カーボンニュートラル実現に資する活動を精力的に行う。更には、異種分野の学際的グループを形成し、協力して新たな触媒材料およびその反応の解明・制御に取り組むことで、触媒材料・反応科学の学術基盤の創成に向けた潮流を起こし、知見の集約(渦)拠点をこの名城大学に創出することを目指す。